視点を入れ替え、対応を振り返ることでコミュニケーションへの気づきを促し、
家庭内における当事者との関係性改善をサポートします。

ご家族がひきこもりや精神疾患への理解を深め、ひきこもる本人の来所・受診がスムーズに進むための声かけなど、
具体的な対話スキルを 5 つのステップで習得できるように実践力の向上を目指すものです。
評価(ひょうか) ひきこもりの状況を理解する
聴く(きく) 傾聴による相談しやすい居場所づくり
声かけ(こえかけ) ポジティブな行動変化のための適切な声かけ
求める(もとめる) 専門家の支援を求める
リラックス 家族自身の心の余裕を大切にする
ひきこもり家族支援VRは、支援の5つのステップに基づき、支援者が当事者と向き合うために必要なスキルを実践的に学べるよう設計されています。各ステップには複数の場面が設定されており、豊富な体験を通して、より深い理解と効果的なスキルの習得を目指すことができます。

3日間の家族支援プログラムに参加した参加者のデータを分析した結果、
ひきこもり当事者の社会参加や支援利用開始などの実際の行動変化が観察されました。
本サービスは、当事者と生活する家族の方を対象としたプログラムです。家庭内で適切な関わりを実践するために、VR体験を通してコミュニケーションのポイントを学習するだけでなく、家庭内で実践するための練習まで同時に取り組むことができます。

全てのVRコンテンツは「状況体験」「工夫発見」「実践練習」の3つのパートで構成されています。
はじめによくある場面を体験し、次にどのようなポイントが重要であるかを学び、最後にVR上で実際に練習するという流れで体験していきます。

家族視点で、ついついやってしまいがちな対応を体験するパートです。当事者とのやり取りの中で、感情的になってしまったり、操作的になってしまうことで、思いが伝わらない場面を体験します。心の仕組み図による振り返りで、背景にある自分自身の気持ちにも目を向けていきます。

視点を入れ替えて、当事者視点で先程の体験を振り返るパートです。客観的に自らの態度や対応を観察し、どのような工夫が必要であったかを考えます。VR空間上の支援者が進行をリードしてくれるので、実施者の負担も軽減されます。
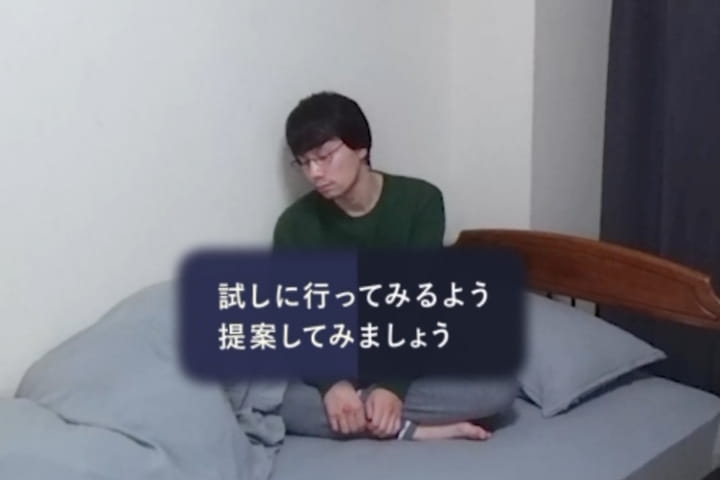
VR上で登場人物に対して、実際に声かけの練習を行うパートです。体験前に適切なモデルが示されるので、表情や間のとり方、共感の方法といった具体的な方法についても学習をすることができます。リアルな空間の中で実践的な練習を重ねることで、日常生活での般化を目指します。
コンテンツサンプル

支援者向けのワークシートや、支援のステップをまとめた冊子も用意しています。
VR体験と組み合わせることで、より効果的な研修が可能です。
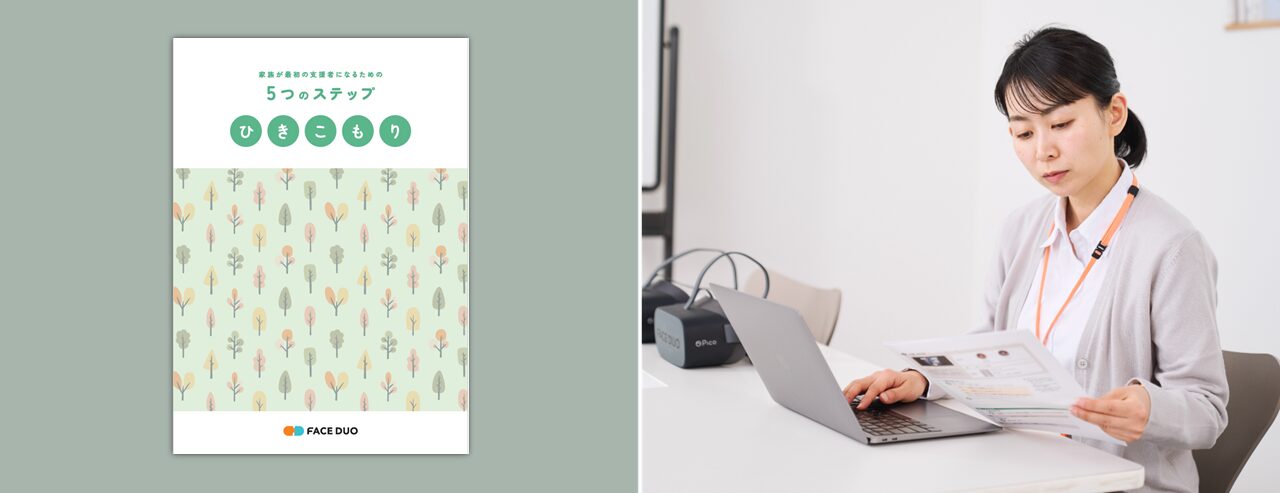
FACEDUOは家族だけでなく、ひきこもりの当事者の方に向けたプログラムも用意しています。当事者のプログラムでは、ソーシャルスキルトレーニングVRを応用することで、社会生活を送る上で必要なスキルを身につけるための「予行練習」が可能となります。

本サイトでは、医療関係者向けの情報と、
一般の方向けの情報を提供しています。
閲覧する情報をお選びください。
医療・福祉・介護・自治体・ヘルスケア事業に従事される方向けに、専門的な情報を提供しています。
患者さまやそのご家族をはじめ、一般の方へ向けて健康や製品に関する情報をわかりやすく提供しています。
認知症介護に関するセミナーや自治体等のイベントでの展示でFACEDUOを体験できる情報を各エリアで掲載しています。
認知症ケア支援VRを体験したい方はこちらを検索してください。
加藤 隆弘 先生
北海道大学大学院医学研究院 神経病態学分野 精神医学教室 教授
(ひきこもり研究ラボ@九州&北海道 代表)
「社会的ひきこもり」は、6ヶ月以上にわたり就労・学業など社会参加を回避し自宅に留まっている現象であり、国内では140万人以上の方々がひきこもり状態にあると推計されています。ひきこもりの背景としてうつ病など精神疾患の併存が珍しくありません。精神疾患やひきこもりに対する偏見や誤解のために、本人ばかりでなく家族も相談機関や精神科などの医療機関への来所・受診をためらい、見て見ぬふりをしてしまうことが少なくありません。その結果ひきこもり支援の開始が大幅に遅れ、8050問題など長期化・高齢化が社会問題となっています。私たちは家族がひきこもりや精神疾患への理解を深め、ひきこもる本人の来所・受診がスムーズに進むことを願い、家族からの声かけなど具体的な対話スキルを習得できるように、ロールプレイを盛り込んだVRプログラムを開発しました。こうしたプログラムを基にした家族向けの教育支援が全国のひきこもり支援機関で活用されることで、ひきこもる本人による直接の来所・受診が早まり、ひきこもりの長期化解消の一助となることを期待しています。